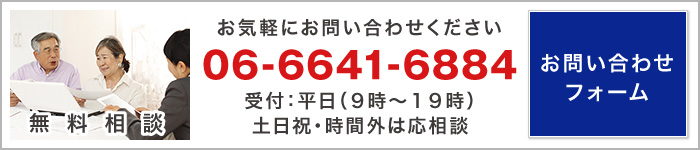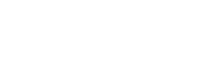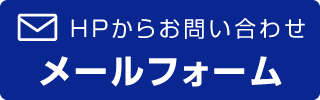先日、『相続人がいない場合、相続財産はどうなるか』について簡単にご説明しました。
その中の、『特別縁故者への財産分与』についてご説明したいと思います。
特別縁故者とは、
(1)被相続人と生計を同じくしていた者
(2)療養看護に努めた者
(3)その他被相続人と特別の縁故があった者
とされています。
具体的には、長年連れ添ってきた内縁関係の配偶者などが代表的な例になります。
単に親戚(いとこである)場合や、療養看護に努めたといっても相当の報酬を得て業務として行っていた場合は特別縁故者に該当しないと思われます。
また、特別の縁故があれば、寺院や学校、市町村などの法人も特別縁故者となれます。
特別縁故者として財産分与の請求をするためには、まず家庭裁判所に相続財産管理人選任の申立をして、相続債権者・受遺者に対する請求申出の公告・催告、相続人捜索の公告などを経る必要があります。
相続財産管理人が行った相続人最後の相続人捜索期間満了後3ヶ月以内に、家庭裁判所に申立をし、家庭裁判所は縁故の内容から、相当な分与を判断します。
遺産の整理(清算)を開始してもらう必要があります
申立を行えば必ず全てもらえるものではなく、家庭裁判所の裁量により、分与するか、するとしたらどれだけ分与するかが決まります。
特別縁故者として財産分与を受けるには非常に手間がかかり、また分与されるかどうかは家庭裁判所の判断によるため、相続人以外の人に財産を確実に渡したい場合には、あらかじめ遺言書を作成されることをお勧めします。
遺言作成についてはほつま相続相談所へご相談ください。
遺産相続や遺言書の作成は、多くの人にとって一生に一度あるかないかの大きな出来事です。
何から手をつければいいかわからない、専門的な手続きが難しそう、といった不安を抱えるのは当然のこと。
私たち「ほつま相続相談所」は、そんな皆さまの「身近な専門家」として、大阪市浪速区や兵庫をはじめとする関西圏の皆さまをサポートしてきました。
初回相談は無料。複雑な手続きも、分かりやすく丁寧にご説明します。
「誰に相談すればいいのだろう?」と悩んでいらっしゃるなら、まずは一度、お話を聞かせてください。
皆さまの疑問や不安に寄り添い、最適な解決策を一緒に見つけていきます。
相続手続きや遺言書作成に関するご相談は、お気軽にお問い合わせください。