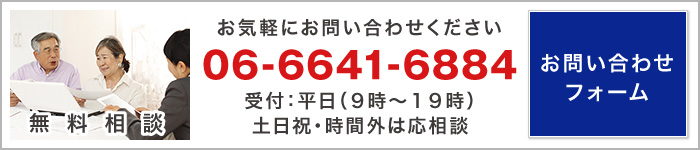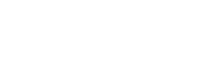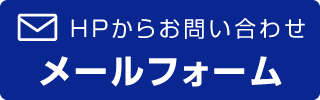相続人は、被相続人が死亡したときに存在している必要がありますので、相続開始以前に死亡した場合や、相続開始後に生まれた場合は、相続はできません。(ただし、相続開始以前に相続人が死亡した場合には代襲相続が発生します。)
では、相続開始時に胎児であった場合はどうなるのでしょうか。
胎児は、原則として権利能力がなく、出生により初めて権利能力を有しますが、相続においては、例外的に胎児も生まれたものとみなされるので、胎児も相続人となります。
ただし、胎児が死産であった場合には、上記の規定は適用されません。
つまり、胎児であっても遺産分割協議をすることができ(実際には胎児の母、若しくは胎児と母が利益相反する場合には家庭裁判所で選任された特別代理人が協議に参加します)、不動産の相続も「亡何某妻何某胎児」として胎児名義の登記をすることも可能です。
死産であった場合は遺産分割協議のやり直しや行った相続登記について更正登記をする必要があり、手続が煩雑になりますので、急がなければならない事情がなければ無事に生まれてから相続手続きを進められた方がいいでしょう。
相続人の中に胎児や未成年者がいる場合は、特別代理人の選任が必要であることもありますので、そのような場合には専門家に相談されてみてください。
当事務所では出張相談に対応しておりますのでお気軽にご相談ください。
遺産相続や遺言書の作成は、多くの人にとって一生に一度あるかないかの大きな出来事です。
何から手をつければいいかわからない、専門的な手続きが難しそう、といった不安を抱えるのは当然のこと。
私たち「ほつま相続相談所」は、そんな皆さまの「身近な専門家」として、大阪市浪速区や兵庫をはじめとする関西圏の皆さまをサポートしてきました。
初回相談は無料。複雑な手続きも、分かりやすく丁寧にご説明します。
「誰に相談すればいいのだろう?」と悩んでいらっしゃるなら、まずは一度、お話を聞かせてください。
皆さまの疑問や不安に寄り添い、最適な解決策を一緒に見つけていきます。
相続手続きや遺言書作成に関するご相談は、お気軽にお問い合わせください。