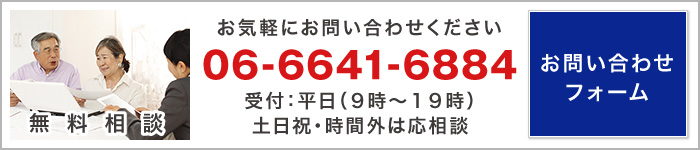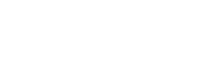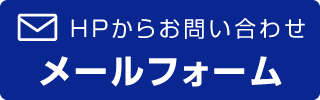相続手続きでは、亡くなった方の戸籍を出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本・原戸籍謄本の一式が必要になります。
これは、誰が相続人であるかを特定するためです。
実際、ご相談に来られたお客様の中には、異父または異母兄弟がいたなどの事実が戸籍を確認して判明したこともありました。
では、『相続人』についてご説明します。
・配偶者は必ず相続人になります。
・第一順位の相続人・・・子(子が被相続人より先に死亡している場合は孫(代襲相続))
・第二順位の相続人・・・両親(両親が被相続人より先に死亡している場合は祖父母)
・第三順位の相続人・・・兄弟姉妹(兄弟姉妹が被相続人より先に死亡している場合は甥・姪(代襲相続)※甥・姪が死亡していても再代襲はありません)
※ 第二順位の相続人・第三順位の相続人は、先順位の相続人がいる場合は相続人になりません。
相続人にあたるのかわかりにくいケースの一例
・内縁の夫または妻・・・婚姻届を提出していなければ、実質夫婦として長期間生活をしていたとしても相続人になりません。相続財産を残したい場合には遺言書で遺贈等をする必要があります。
・養子縁組をしていない前夫・前妻の子・・・相続人になりません。相続財産を残したい場合には遺言書で遺贈等をする必要があります。
・相続放棄をした相続人の子や孫・・・相続人となりません。先に死亡した場合の代襲相続と違い、相続放棄を行った場合は、子や孫は相続人になりません。
・異父兄弟・異母兄弟・・・相続人となります。例としては、婚姻前の子や、再婚後に出生した子などです。
・養子又は養親・・・養子縁組により相続人になります。養子縁組を行っているか、離縁をしているかについて戸籍で確認する必要があります。
・包括受遺者・・・相続人にはなりませんが、相続人と同じ権利義務を有しますので、遺産分割協議に参加する必要があったり、拒否するには裁判所へ申述が必要となります。
せっかく遺産分割協議をしても相続人を欠く遺産分割は無効となったり、法定相続で相続する場合の割合に影響しますので、相続人の特定は、相続手続きにおいて非常に重要な作業となります。
相続人の特定が難しい場合は、専門家に相談し、戸籍をみてもらうことをおすすめします。
遺産相続や遺言書の作成は、多くの人にとって一生に一度あるかないかの大きな出来事です。
何から手をつければいいかわからない、専門的な手続きが難しそう、といった不安を抱えるのは当然のこと。
私たち「ほつま相続相談所」は、そんな皆さまの「身近な専門家」として、大阪市浪速区や兵庫をはじめとする関西圏の皆さまをサポートしてきました。
初回相談は無料。複雑な手続きも、分かりやすく丁寧にご説明します。
「誰に相談すればいいのだろう?」と悩んでいらっしゃるなら、まずは一度、お話を聞かせてください。
皆さまの疑問や不安に寄り添い、最適な解決策を一緒に見つけていきます。
相続手続きや遺言書作成に関するご相談は、お気軽にお問い合わせください。